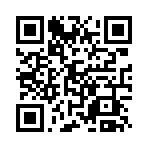心理職とは何か?~心理職による訪問支援を通して見えてくること
東日本大震災が起きたのが2011年3月。早7年という歳月が流れたが、私は色々縁あって、その被災者支援に今も携わっている。
東日本大震災の特徴として、福島県での原発事故が挙げられる。その原発事故の避難者数はピーク時で16万人、現在でも5万人。
静岡県にも約500人、200世帯ほどが暮らしている。私はその訪問相談支援に携わり、4年半が経とうとしている。
少し話は変わるが、心理職というのはつくづく曖昧で、わかりにくい職種だと思う。昨年の法案の成立によって、公認心理師という、日本における心理職としては初めて国家資格ができることになったわけだが。その段階になっても尚、おそらく当の心理職の者自身も、心理職がなんであるかなんて、わかっていないんじゃないか。
というのも、つい先だって、訪問相談支援は心理の仕事ではない。などとほざ...(失礼(苦笑))言われたのだ。
現に訪問相談支援をしている私の目の前で。
絶句して、私には??がとんだ。
理由をきくと、だって被災地では精神科医は身分すら隠して、訪問相談をしていたから。
は?
私たちは精神科医じゃないじゃん。心理職じゃん。
私達の仕事を何だと思っているんだろう?
そうね。
あなた達は心理職だけの訪問相談支援に携わっていないわね。
やってみてもいないのに。わかった顔するのね。
上等だ。
知ってた?心理職なんて、誰も知らない仕事だって。精神科医以上に知られてない、理解されていない仕事だって。
そしてだからこそ、まず与えられたことをやってみるのが仕事だってこと。
ちなみに、傾聴にはやったことの無いことを吸収する力はあっても、決して知ったかぶりや自分がやったふりはしてはいけないんだということを、知らなかった??
さあ、私の飲み込んだ暴言はさておいて(笑)
心理職のアウトリーチというのは確かに、様々にリスクはある。
専門である心理職の側にも、受け手であるクライアントの側にも。
正確に言うと、災害時支援におけるアウトリーチでは、クライアントはまだ、クライアントであるかどうかわからないとも言える。
ただ、災害時はまた誰にとっても心理的危機に曝されているときである。支援希求やまして心理的な意味での相談希求は自覚的では無いにせよ、だからこそ注意深く寄り添っていく必要はあるのではないだろうか。
私達心理職はどちらかというと、相談室という限られた空間の中で話を聴くことが多い。
だからその中で、出来る限りの想像力を働かせていかないと、その人の問題が見えないことも多い。
アウトリーチでは、それをリアルに飛び込んでいって見れるわけなんだけど。
それを枠がなくて怖いと言った人がいた。
それは確かにそう。
相談室内ではどっぷりと共感してればいいけれど、相手の家の中となったらそうはいかない。
だけど、相談室内でカウンセリングする、話を聴くということはそもそも、ひどく不自然で、ともすると傲慢さを作り出すものかもしれない。
相談室内が自分たち心理職の職場であり、そこに来ない限りクライアントでないとか。
来ることにどれだけの大きなハードルがあるかなんて、忘れていて。
来て当然。だから心を開いて当然。のような感覚を心理職として持っているのだとしたら、それは傲慢以外の何物でも無いのではないだろうか。
クライアントを訪問して、散らかった室内を、手を出して、片付けるのではなく、かと言ってボーッと見過ごす訳でもなく。
時に役に立たない娘や嫁の振りをしながら(だってそうでないと、「やって欲しい」オーラを受けなきゃならないから)、心理職を全うする。
その人の心理的な健康や健全な生活を取り戻すためのヒントを必死に探すのだ。
アウトリーチは心理職にとっては、とてもしんどい作業でもある。役に立たない時も多いから、無力感も大きい。
そんな中で、一つ思い浮かべる姿がある。
誰のエピソードだったか。ある治療者の優れた治療者である例えの一つとして、ある鬱々と日々を暮らしていた女性に一言、「花を植えなさい」と言った。しばらくするとその女性の鬱はみるみる良くなって言ったという。
その人は以前、花の手入れが好きで、端正こめて育てていた。その名残を、その女性の自宅の庭先に垣間見たのだという。
これはおそらく、アウトリーチでなければ、わからなかったことではないか。
快復してくれば、その方はかつての自分の好きだったこと、趣味などについて語ることはあっても。
鬱々と落ちた状態ではまず、相談室内で聞き取ることはできないだろうし、イメージもしづらい。
どこにいても、どういう形でも、何をしていても、心理職であることを忘れなければ。
心理職だから心理的なことを聴き出せるはず(聴き出すべき?)とか。傲慢な意味ではなく、あるがままを観察し、全身で聴き取っていく作業の中に、その人の快復やより健全な生活のためのヒントを見つけていく。
それが本来的な意味での心理の仕事なんだとしたら、どうだろう。
それは時には余計なことかもしれない。
でもお節介でもいいじゃない。
余計なお世話と言われたら、そんな雰囲気でも感じたら言えばいい。「ごめんね。」と普通に。そして、もしできるなら、丁寧に伝えた理由を伝えること。
私の中で忘れられないのは、小2のとき同じクラスだった場面緘黙の女の子。
なぜだかその子と二人遊んだ時に、私はすごく困ったわけでもなく、絵本を二人で取り出して、代わる代わる読み聞かせを始めた。その子も小さい声で、私の好きな絵本を読んでくれて楽しかった。
その後、その子は給食の牛乳を頑張って飲んで、それをみんなで応援したり。小さな声で、教室でも音読するようになったり。徐々に変わり始めた。
それは断片的な記憶だけれど、私の中に残っている。あれは一つの心理的な支援ではなかったか。
そうした一つ一つを場所を選ばず、形に拘らず、柔らかに、ただただ、続けていけたらと思うのです。
臨床心理士 新谷
☆カウンセリング
初回90分 9,000円+税
以降50分 7,000円+税
☆トラウマへのホログラフィートーク
単回 9,000円+税
☆心理的逆転を解消する~直したいのに直らない。そんな時に~
モニター募集3名まで!
モニター価格...単回 5,000円
東日本大震災の特徴として、福島県での原発事故が挙げられる。その原発事故の避難者数はピーク時で16万人、現在でも5万人。
静岡県にも約500人、200世帯ほどが暮らしている。私はその訪問相談支援に携わり、4年半が経とうとしている。
少し話は変わるが、心理職というのはつくづく曖昧で、わかりにくい職種だと思う。昨年の法案の成立によって、公認心理師という、日本における心理職としては初めて国家資格ができることになったわけだが。その段階になっても尚、おそらく当の心理職の者自身も、心理職がなんであるかなんて、わかっていないんじゃないか。
というのも、つい先だって、訪問相談支援は心理の仕事ではない。などとほざ...(失礼(苦笑))言われたのだ。
現に訪問相談支援をしている私の目の前で。
絶句して、私には??がとんだ。
理由をきくと、だって被災地では精神科医は身分すら隠して、訪問相談をしていたから。
は?
私たちは精神科医じゃないじゃん。心理職じゃん。
私達の仕事を何だと思っているんだろう?
そうね。
あなた達は心理職だけの訪問相談支援に携わっていないわね。
やってみてもいないのに。わかった顔するのね。
上等だ。
知ってた?心理職なんて、誰も知らない仕事だって。精神科医以上に知られてない、理解されていない仕事だって。
そしてだからこそ、まず与えられたことをやってみるのが仕事だってこと。
ちなみに、傾聴にはやったことの無いことを吸収する力はあっても、決して知ったかぶりや自分がやったふりはしてはいけないんだということを、知らなかった??
さあ、私の飲み込んだ暴言はさておいて(笑)
心理職のアウトリーチというのは確かに、様々にリスクはある。
専門である心理職の側にも、受け手であるクライアントの側にも。
正確に言うと、災害時支援におけるアウトリーチでは、クライアントはまだ、クライアントであるかどうかわからないとも言える。
ただ、災害時はまた誰にとっても心理的危機に曝されているときである。支援希求やまして心理的な意味での相談希求は自覚的では無いにせよ、だからこそ注意深く寄り添っていく必要はあるのではないだろうか。
私達心理職はどちらかというと、相談室という限られた空間の中で話を聴くことが多い。
だからその中で、出来る限りの想像力を働かせていかないと、その人の問題が見えないことも多い。
アウトリーチでは、それをリアルに飛び込んでいって見れるわけなんだけど。
それを枠がなくて怖いと言った人がいた。
それは確かにそう。
相談室内ではどっぷりと共感してればいいけれど、相手の家の中となったらそうはいかない。
だけど、相談室内でカウンセリングする、話を聴くということはそもそも、ひどく不自然で、ともすると傲慢さを作り出すものかもしれない。
相談室内が自分たち心理職の職場であり、そこに来ない限りクライアントでないとか。
来ることにどれだけの大きなハードルがあるかなんて、忘れていて。
来て当然。だから心を開いて当然。のような感覚を心理職として持っているのだとしたら、それは傲慢以外の何物でも無いのではないだろうか。
クライアントを訪問して、散らかった室内を、手を出して、片付けるのではなく、かと言ってボーッと見過ごす訳でもなく。
時に役に立たない娘や嫁の振りをしながら(だってそうでないと、「やって欲しい」オーラを受けなきゃならないから)、心理職を全うする。
その人の心理的な健康や健全な生活を取り戻すためのヒントを必死に探すのだ。
アウトリーチは心理職にとっては、とてもしんどい作業でもある。役に立たない時も多いから、無力感も大きい。
そんな中で、一つ思い浮かべる姿がある。
誰のエピソードだったか。ある治療者の優れた治療者である例えの一つとして、ある鬱々と日々を暮らしていた女性に一言、「花を植えなさい」と言った。しばらくするとその女性の鬱はみるみる良くなって言ったという。
その人は以前、花の手入れが好きで、端正こめて育てていた。その名残を、その女性の自宅の庭先に垣間見たのだという。
これはおそらく、アウトリーチでなければ、わからなかったことではないか。
快復してくれば、その方はかつての自分の好きだったこと、趣味などについて語ることはあっても。
鬱々と落ちた状態ではまず、相談室内で聞き取ることはできないだろうし、イメージもしづらい。
どこにいても、どういう形でも、何をしていても、心理職であることを忘れなければ。
心理職だから心理的なことを聴き出せるはず(聴き出すべき?)とか。傲慢な意味ではなく、あるがままを観察し、全身で聴き取っていく作業の中に、その人の快復やより健全な生活のためのヒントを見つけていく。
それが本来的な意味での心理の仕事なんだとしたら、どうだろう。
それは時には余計なことかもしれない。
でもお節介でもいいじゃない。
余計なお世話と言われたら、そんな雰囲気でも感じたら言えばいい。「ごめんね。」と普通に。そして、もしできるなら、丁寧に伝えた理由を伝えること。
私の中で忘れられないのは、小2のとき同じクラスだった場面緘黙の女の子。
なぜだかその子と二人遊んだ時に、私はすごく困ったわけでもなく、絵本を二人で取り出して、代わる代わる読み聞かせを始めた。その子も小さい声で、私の好きな絵本を読んでくれて楽しかった。
その後、その子は給食の牛乳を頑張って飲んで、それをみんなで応援したり。小さな声で、教室でも音読するようになったり。徐々に変わり始めた。
それは断片的な記憶だけれど、私の中に残っている。あれは一つの心理的な支援ではなかったか。
そうした一つ一つを場所を選ばず、形に拘らず、柔らかに、ただただ、続けていけたらと思うのです。
臨床心理士 新谷
☆カウンセリング
初回90分 9,000円+税
以降50分 7,000円+税
☆トラウマへのホログラフィートーク
単回 9,000円+税
☆心理的逆転を解消する~直したいのに直らない。そんな時に~
モニター募集3名まで!
モニター価格...単回 5,000円