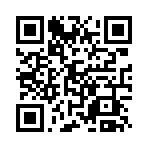フクシマからの避難者を訪ねて ~震災から4年がすぎた現在の人々の心象~
つい先日、福島県から静岡県への避難者宅への家庭訪問を実施しました。
昨年度より福島県から静岡県臨床心理士会に委託され、私はその県臨床心理士会の一員として、家庭訪問を行っています。
手探りで昨年度末から本格的にスタートしましたが、そこには「被災による避難者」というだけでは括れない、さまざまな家族の姿、人々の想いがありました。
福島県からの避難者宅へは事前アンケートを実施後、連絡先を頂けたお宅にはまず電話で聴取を行い、アポをとり、家庭訪問に伺わせていただいています。
臨床心理士としては、こうしたアウトリーチによるというのは、特殊なことではありますし、面談という枠...言ってみるとカウンセリングを行うためのカウンセラーの側の基本的なペース...を作りにくいとは言えます。
でもそうした本来の枠を越え、一歩家庭の中に踏み込んでいく関わりが必要とされているのだと理解し、私たちは「ふくしま家庭のサポート」と名付けています。
東日本大震災から4年が経ち、少しずつ過去になりつつある中、あえてスタートしたこの事業。
初回訪問は福島県の職員の方と一緒に行うのですが、その方からいただいた大切な言葉があります。
「公的支援が途絶えた後からが本当の支援です」
私たちは「被災による避難者」にどんなイメージを抱くでしょうか。
"話を聴く"ことを生業にしながらも、一つ一つ訪問先の方のお話を伺いながら、私の中にもまたある「被災による避難者」のイメージを手放していく作業のように感じることがあります。
今回の震災の場合、ご存じのの通り福島県は原発という問題もまた抱えています。
「戻りたいけど戻れない」
「いつ戻れるのか」
そしてその決断をすることができるときはいつなのかすら、わからないまま。
一方で、公的な支援は当然のことのように、年々減らされていきます。
どの方も避難生活ではありますが、不満を持っているわけではありません。
むしろ、不満を抱いてはいけない。
良くしていただいて感謝している。
感謝しなくては。
...と話される方が多くいます。
それはともすると、避難者であるがゆえの
「罪悪感」のように私の目には映ることがあります。
「被災者であるから」失ったことによるダメージはもちろんありますし、それは誰もが想像することかもしれません。でもそれが、家族にとって、その人にとって、どんな影響となって表れるか、表れてきているか。
想像の範囲を越え、その家庭によってさまざまな広がりを見せています。ここに全ては書けませんが、家庭の、個人の問題が、複雑に巧妙に、震災の被害に絡み合い、その人の人生を揺るがす大きなものとなっていることは確かです。
今回の震災特有の"見えない恐怖"もまたさまざまな形で、大きな葛藤を生んでいます。
福島県は本来なら自然豊かな土地であり、親戚家族のつながりの強い、正に"絆"というのはこの県を表すのにぴったりなワードだと感じます。
でも帰れない。
帰ったとしても、以前のようには故郷の自然にも触れられない(地域もある)。
今の静岡での生活は安全だけれど、本当の安心ではない。
なぜなら今までのような家族の形はないから。
暮らしには慣れたけれど、まるで長い夢の中にいるようだ...とどこか現実感が持てないのも頷けます。
私たちは聴くことしかできないことも多くあります。
でもそれは、こうした特殊なアウトリーチ活動に限ったことではありません。
3.11があって良かったとは誰も思いません。
でも、避難してきた場所としてではなく、「静岡にきて良かった」と「きた場所が静岡で良かった」と思っていただけるよう祈りながら。
迎え入れる私たちは「被災による避難者」というファインダーを外して。
心を尽くしたいと思います。

ハートフルSRS ホームページ
www.heartful-srs.com
問合せ先
heartful-srs@shizuoka.tnc.ne.jp
臨床心理士 新谷
昨年度より福島県から静岡県臨床心理士会に委託され、私はその県臨床心理士会の一員として、家庭訪問を行っています。
手探りで昨年度末から本格的にスタートしましたが、そこには「被災による避難者」というだけでは括れない、さまざまな家族の姿、人々の想いがありました。
福島県からの避難者宅へは事前アンケートを実施後、連絡先を頂けたお宅にはまず電話で聴取を行い、アポをとり、家庭訪問に伺わせていただいています。
臨床心理士としては、こうしたアウトリーチによるというのは、特殊なことではありますし、面談という枠...言ってみるとカウンセリングを行うためのカウンセラーの側の基本的なペース...を作りにくいとは言えます。
でもそうした本来の枠を越え、一歩家庭の中に踏み込んでいく関わりが必要とされているのだと理解し、私たちは「ふくしま家庭のサポート」と名付けています。
東日本大震災から4年が経ち、少しずつ過去になりつつある中、あえてスタートしたこの事業。
初回訪問は福島県の職員の方と一緒に行うのですが、その方からいただいた大切な言葉があります。
「公的支援が途絶えた後からが本当の支援です」
私たちは「被災による避難者」にどんなイメージを抱くでしょうか。
"話を聴く"ことを生業にしながらも、一つ一つ訪問先の方のお話を伺いながら、私の中にもまたある「被災による避難者」のイメージを手放していく作業のように感じることがあります。
今回の震災の場合、ご存じのの通り福島県は原発という問題もまた抱えています。
「戻りたいけど戻れない」
「いつ戻れるのか」
そしてその決断をすることができるときはいつなのかすら、わからないまま。
一方で、公的な支援は当然のことのように、年々減らされていきます。
どの方も避難生活ではありますが、不満を持っているわけではありません。
むしろ、不満を抱いてはいけない。
良くしていただいて感謝している。
感謝しなくては。
...と話される方が多くいます。
それはともすると、避難者であるがゆえの
「罪悪感」のように私の目には映ることがあります。
「被災者であるから」失ったことによるダメージはもちろんありますし、それは誰もが想像することかもしれません。でもそれが、家族にとって、その人にとって、どんな影響となって表れるか、表れてきているか。
想像の範囲を越え、その家庭によってさまざまな広がりを見せています。ここに全ては書けませんが、家庭の、個人の問題が、複雑に巧妙に、震災の被害に絡み合い、その人の人生を揺るがす大きなものとなっていることは確かです。
今回の震災特有の"見えない恐怖"もまたさまざまな形で、大きな葛藤を生んでいます。
福島県は本来なら自然豊かな土地であり、親戚家族のつながりの強い、正に"絆"というのはこの県を表すのにぴったりなワードだと感じます。
でも帰れない。
帰ったとしても、以前のようには故郷の自然にも触れられない(地域もある)。
今の静岡での生活は安全だけれど、本当の安心ではない。
なぜなら今までのような家族の形はないから。
暮らしには慣れたけれど、まるで長い夢の中にいるようだ...とどこか現実感が持てないのも頷けます。
私たちは聴くことしかできないことも多くあります。
でもそれは、こうした特殊なアウトリーチ活動に限ったことではありません。
3.11があって良かったとは誰も思いません。
でも、避難してきた場所としてではなく、「静岡にきて良かった」と「きた場所が静岡で良かった」と思っていただけるよう祈りながら。
迎え入れる私たちは「被災による避難者」というファインダーを外して。
心を尽くしたいと思います。

ハートフルSRS ホームページ
www.heartful-srs.com
問合せ先
heartful-srs@shizuoka.tnc.ne.jp
臨床心理士 新谷